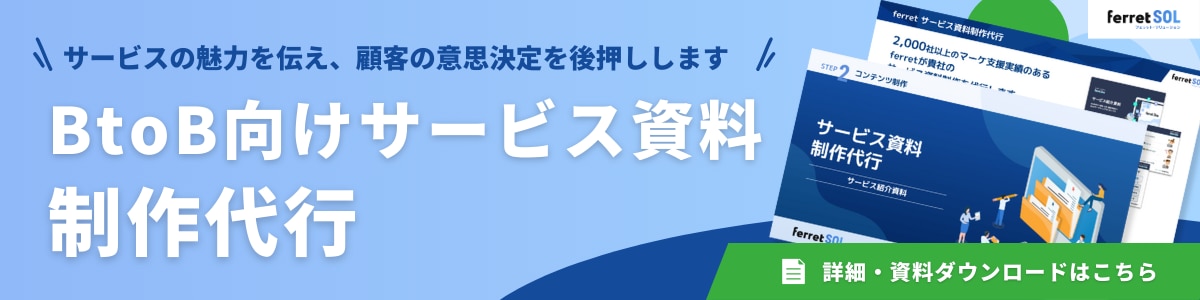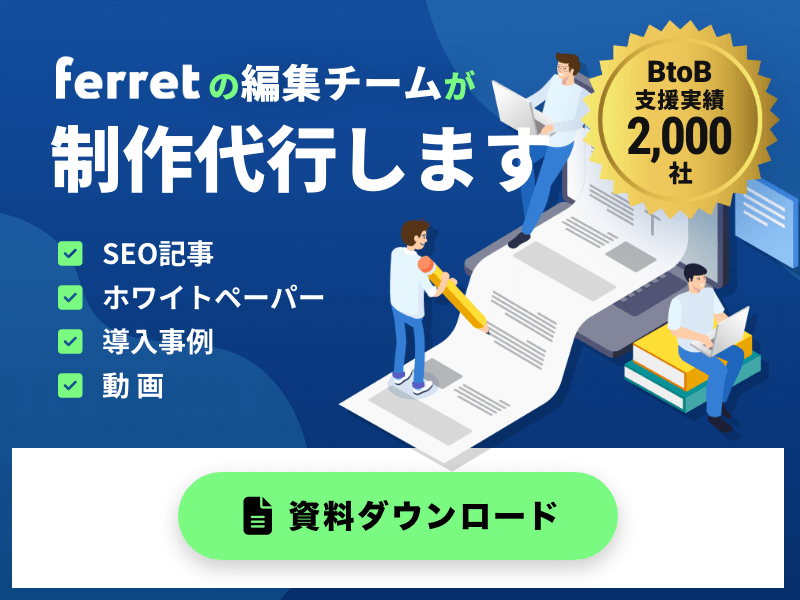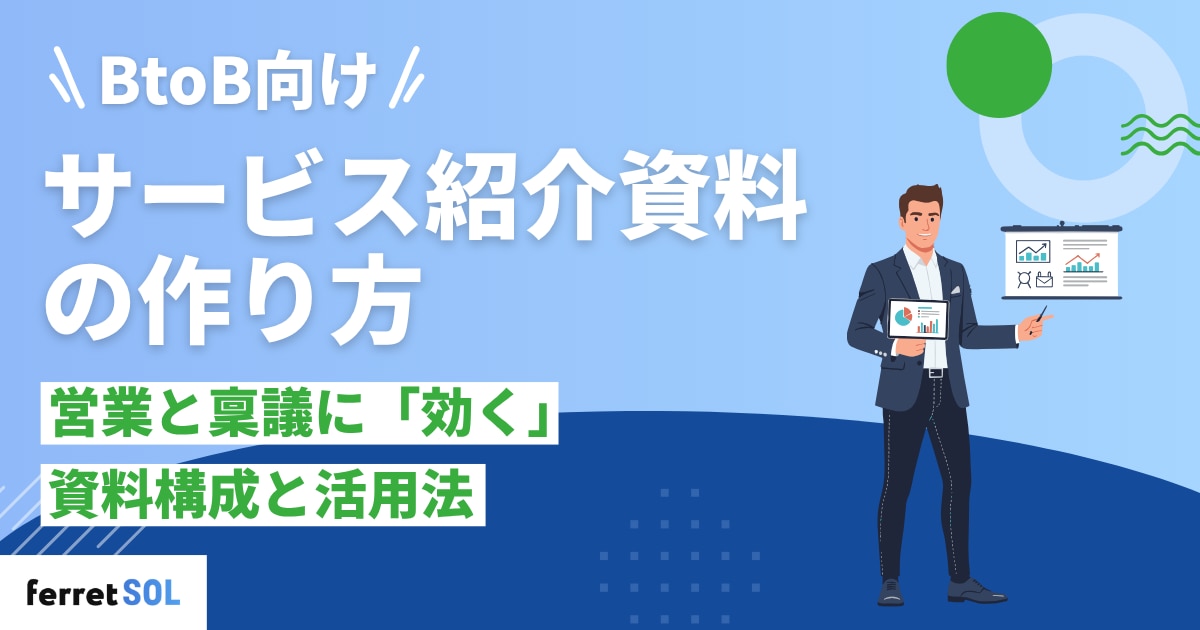
【BtoBサービス紹介資料の作り方】営業と稟議に「効く」資料構成と活用法
BtoBマーケティング担当者の方、サービス紹介資料は「作ること」自体が目的になっていませんか?
「Webサイトの集客はできているけれど、商談や受注に繋がる資料になっていない」、「営業に資料を活用してもらえない」といった課題に直面している中堅・中小企業のマーケターの方は少なくありません。特にリソースが限られている企業様にとって、資料の制作にかけた時間とコストがムダになるのは避けたいところです。
BtoBビジネスにおけるサービス紹介資料は、BtoCの販促資料とは異なり、「社内検討と稟議を促進するツール」という重要な役割を担っています。この役割を果たすには、資料の構成以前に、「明確な戦略設計」が不可欠です。
本記事では、2,000社以上のBtoBマーケティング支援で培った知見に基づき、サービス紹介資料を「作る」から「売上に繋げる」資料に変えるための構成、戦略設計、そして営業連携の具体的なノウハウを解説します。
あわせて読みたい:成果につながるBtoBホワイトペーパーの作り方|CV率向上を実現する設計
目次[非表示]
BtoBサービス紹介資料が「売上」に貢献する3つの役割
BtoCの「販促資料」とは異なるBtoBの役割
BtoC(消費者向け)の販促資料が「個人の購買意欲の喚起」を主目的とするのに対し、BtoB(法人向け)のサービス紹介資料の役割は「社内検討と稟議を促進するツール」であるという決定的な違いがあります。
BtoB商材は高額で、「意思決定に関わる人が複数」にわたるため、担当者が「良い」と思っても、その上長である決裁者や事業責任者の承認が必要になります。
資料は、担当者の手を離れて「一人歩き」することが前提です。そのため、資料には以下の要素を論理的に盛り込み、「担当者が上長を説得できるだけの根拠」を提供する必要があります。
- 論理的な根拠:
- 「なぜ今、この課題を解決する必要があるのか」という市場や事業の背景
- 「その解決策として、なぜこのサービスが最適なのか」という競合優位性
- 費用対効果:
- コスト(導入費用・運用費用)に対して、売上や効率化(リソース削減)のインパクトがどれだけあるか
資料の目的を「売上向上」と「コスト削減」のどちらの文脈で設定するかによっても、訴求すべき要素が変わってくるため、資料の設計は、「誰を動かしたいか」という社内での役割を理解することから始まります。
購買プロセスにおける資料の「態度変容」の役割
BtoBの購買プロセスにおいて、顧客は「営業担当者と接触する前に、意思決定プロセスの67%を完了」させているというデータがあります。つまり、資料は、顧客の検討度が「顕在層」から「明確層」へと移行する「最後のひと押し」となる重要なコンテンツです。
資料のダウンロードは、顧客の検討段階が以下のように進んでいる状態を示唆します。
- 顕在層:「課題への自覚があり、解決策を模索中」
- 態度変容のきっかけ: 自社の課題解決に役立つ具体的な解決策や、サービスの特徴を知る
- 明確層へ:「具体的な発注先を絞り込んでいる」、あるいは「すぐに商談したい」という行動を促す
資料ダウンロードというライトな接点を増やし、その後も関連コンテンツで継続的に情報を提供することで、顧客の「この課題なら、この会社に任せたい」という「第一想起」を強化する仕組みが資料の核となるのです。資料ダウンロードを皮切りに、顧客の「検討段階が可視化」され、「最適なタイミングでの営業アプローチ」が可能になる、という点も資料の重要な役割です。
資料が成果に繋がらない組織の「失敗パターン」
「資料を作っても営業に活用してもらえない」「ダウンロード数は多いけれど商談化しない」という失敗は、「戦略設計の甘さ」が原因である場合がほとんどです。
多くのBtoBマーケティング組織が陥る失敗パターンは、以下の通りです。
- 場当たり的な施策の実行: サイトのターゲット設定や提供価値が曖昧なまま、流行のテーマで資料を作ってしまう(「作ること」が目的化)
- 初期戦略設計の甘さ: 資料が社内検討で使われることを想定せず、営業が稟議を通すための論理的根拠(競合比較、費用対効果など)が不足している
- 部門間の分断: マーケティング部門のKPI(リード獲得数)と営業部門のKPI(受注数)が異なり、「質の高いリードの定義」が共有されていない
これらの失敗は、最終的に「リードが営業の効率を悪化させる」という結果に繋がります。この課題を解決するためには、まず資料作成の「土台となる戦略を固める」ことが不可欠です。
成果につながるサービス紹介資料の「核」は「誰の、何を、どのように解決するか」の言語化
資料が成果に繋がるかどうかは、構成やデザインよりも、「資料の核」となる「戦略設計」によって決まります。まずは以下の3つの要素を明確にしましょう。
- ターゲット: 誰に読んでほしいか(担当者か、経営層か)
- 提供価値: 読者の課題をどう解決できるか(顧客メリット)
- 競合優位性: 他社ではなく、貴社を選ぶべき論理的根拠
資料作成前に決めるべき「ターゲット」と「提供価値」
資料を作る前に、「誰を動かしたいか(ターゲット)」と「資料を通じて何を伝えたいか(提供価値)」を明確にすることが重要です。
ターゲット | 目的とするアクション | 資料に盛り込むべき情報(訴求の核) |
|---|---|---|
担当者(マネージャー/課長) | 「サービスを自分ごととして理解する」→「上長への推薦」 | 具体的な課題解決の手順、ツールの操作性、日々の業務効率化、競合比較(機能・操作性軸) |
決裁者(経営層/事業部長) | 「稟議・導入の承認」→「予算の確保」 | 事業へのインパクト(売上向上)、費用対効果(コスト削減)、同業他社の導入実績、リスク(セキュリティなど) |
特にBtoBでは「組織ターゲット」を明確にし、「その組織の課題をどう解決できるか」という「顧客メリット」を明確にすることが、資料の核となります。この段階の設計が甘いと、資料の内容が「自社が売りたい機能」の羅列に偏ってしまい、「読者の知りたいこと」から逸脱してしまいます。
営業連携を前提とした「社内稟議」で使える構成要素
サービス紹介資料は、担当者から決裁者へと「社内稟議」を回ることを前提に構成する必要があります。稟議資料として機能させるために、以下の情報が「過不足なく網羅」されているかを確認しましょう。
稟議で必要になる情報 | 報告者(担当者)の目的 | 決裁者(上長)の判断軸 |
|---|---|---|
価格・プラン | 予算内での実現可能性、費用対効果の試算 | 投資対効果(ROI)、初期投資の妥当性 |
導入事例・実績 | 自社と同業種・同規模の成功イメージ | 企業の信頼性、ネームバリュー、事業へのインパクト |
機能・仕様 | 課題解決に必要な機能の有無 | 競合との差別化(優位性)、将来的な拡張性 |
会社情報・サポート | 導入後の運用負荷の軽減、サポート体制の安心感 | 取引先としての信頼性(経営の安定性)、リスク管理(セキュリティなど) |
資料を「売上向上」と「コスト削減」のどちらの文脈で上申するかによって、必要な構成要素が変わることを念頭に置きましょう。例えば、コスト削減文脈であれば、「運用工数の削減率」や「外注費の圧縮効果」を定量的に訴求するスライドが必要になります。
中堅企業のマーケティング成功事例から学ぶ戦略
従業員100名から500名未満の中堅企業では、「マーケティング専任の担当者が不足」し、「戦略が描けず場当たり的」な施策になっているという課題に直面しがちです。
このような組織が成果を出すためには、資料作成の前に「初期戦略」を明確にすることが不可欠です。初期戦略を明確にすることで、「何を打ち出すべきか」が明確になり、マーケティング部門と営業部門の「認識のズレ」がなくなります。
実際に、弊社のご支援企業様の中には、従業員規模300名程度のIT系企業様が、資料作成を含むWebマーケティングの立ち上げ前に「初期戦略を明確化」しました。これにより、営業部門とマーケティング部門の「認識が統一」され、その後に作成した資料が「営業活動で活用」されるようになり、「商談化率が向上」しました。
戦略設計からコンテンツ制作まで一貫して支援するferretソリューションの考え方は、資料の成果を阻害する「戦略設計の甘さ」という根本原因を解決し、「成果につながる資料」を作るための土台となるのです。
受注率を高める資料の「構成案」と「スライド作成」の具体的手順
資料の目的を達成するための「鉄則構成」(10〜16スライド)
BtoBの意思決定に必要な要素を過不足なく伝えるためには、資料の構成(スライド順)にも「鉄則の型」があります。以下の「10〜16スライド構成」を参考に、自社のサービスに合わせてカスタマイズしてください。
項目 | スライド数(目安) | 目的・役割 |
|---|---|---|
表紙・目次 | 1〜2 | 資料の読み進めるモチベーションを高める |
問題提起(課題) | 1〜2 | 顧客の顕在的・潜在的課題を提示し、共感を得る |
解決策(サービス概要) | 1〜2 | その課題を貴社サービスがどう解決できるかを端的に示す |
機能・サービス詳細 | 2〜3 | 具体的な機能とそれによる顧客メリットを説明 |
導入実績・事例 | 2〜3 | 信頼の獲得と成功イメージの想起を促す |
価格・プラン | 1〜2 | 費用対効果を試算できる具体的な料金体系を提示 |
会社概要・サポート | 1〜2 | 取引先としての信頼性と導入後の安心感を訴求 |
CTA(行動喚起) | 1 | 次のアクション(問い合わせ、デモなど)を明確に提示 |
特に「導入実績・事例」と「価格・プラン」は、「顕在層・明確層へのアプローチ」として重要です。事例は「業界別・課題別」に複数揃え、価格は「初期費用とランニングコスト」を明確に記載しましょう。
各スライドで必ず押さえるべき「訴求ポイント」(上長・決裁者向け)
上長や決裁者(経営層/事業責任者)は、資料を見る際に「費用対効果」と「事業へのインパクト」という視点を持ちます。資料を稟議資料として機能させるために、各スライドで盛り込むべき客観的な情報は以下の通りです。
- 問題提起スライド:
- 業界トレンドや法改正など、マクロな視点から「なぜ今、この課題を解決する必要があるのか」という「緊急性」を示す。
- 「既存のやり方では限界が来ている」という「危機感を刺激」する。
- 機能・サービス詳細スライド:
- 単なる機能の紹介ではなく、「この機能が導入されることで、事業にどのようなインパクトがあるのか」という「メリット」を併記する。
- 競合との「差別化ポイント」を明確にし、他社を選ぶことによる「機会損失」を示唆する。
- 導入実績・事例スライド:
- 売上向上、コスト削減、工数削減など、「定量化された成果」を具体的に記載する。
- 「○○業界No.1」「××部門でシェア1位」などの「権威性」を示す客観的事実やデータを引用する。
営業連携を深め「商談・受注」に繋げる資料の活用法
営業フェーズ(IS/FS)に合わせた資料の「渡し方」と「伝え方」
資料を「作って終わり」にせず、営業チームと連携して「商談率・受注率を向上」させるためには、営業の各フェーズで資料をどう活用すべきかを明確にすることが重要です。
営業フェーズ | 担当者 | 資料の活用方法 |
|---|---|---|
リード獲得直後 | IS(インサイドセールス) | 架電のドアノックツールとして、資料をフックにアポ獲得を促す。顧客の課題に合わせた関連事例をメールで送付する。 |
商談前・商談中 | FS(フィールドセールス) | 競合との差別化を図るための提案資料として活用。顧客の「導入の決め手」となる部分(価格、実績、サポートなど)を強調して提示する。 |
商談後・稟議中 | FS(フィールドセールス) | 稟議資料として活用してもらうため、上長への説明に必要な情報(費用対効果、導入実績など)を再送し、意思決定の後押しをする。 |
特にインサイドセールスにおいては、資料をきっかけに架電することで、「顧客が自覚していなかった潜在ニーズを引き出せる」ことがあります。資料の内容を熟知した営業担当者が、顧客の課題に合わせた「渡し方」と「伝え方」を実践することで、商談の質が高まります。
資料を起点とした「リードナーチャリング」の仕組み
資料をダウンロードしたものの、すぐに商談に至らない顧客(準顕在層)に対しては、資料を起点とした「リードナーチャリング」の仕組みが必要です。
- セグメント設定: 資料のダウンロード情報(業種、役職、課題感)を基に、顧客を「セグメント」する。
- コンテンツの選定: ダウンロードした資料の内容に合わせた「関連コンテンツ」(具体的な事例集、より深いノウハウウェビナーなど)を「ステップメール」で自動配信する。
- 行動の可視化: メール内のリンククリックや、Webサイトの再訪問といった「行動履歴を追跡」し、「検討度が上がったタイミング(MQL化)」を見逃さない仕組みを構築する。
この仕組みの構築には、リード情報と行動履歴を一元管理できるマーケティングツール(MA/CRMなど)と、営業連携のためのデータ連携(SFA/CRM連携など)が不可欠です。
受注に貢献したか測る「KPI」と「ROI試算」の方法
資料の成果を測る指標は、ダウンロード数(CV数)だけでは不十分です。最終的な成果である「商談化率」「受注率」まで追跡し、「事業への貢献度」で評価すべきです。
営業と共有すべきKPIの例としては、「資料ダウンロード後のアポ率」や「資料ダウンロードリードの受注率」などがあります。
また、経営層への報告で必須となるのが「ROI(投資対効果)の試算」です。資料作成にかかったコスト(制作費、広告費)に対して、その資料が「どれだけの売上に貢献したか」を明確にすることで、マーケティング活動への投資の「妥当性」を示すことができます(ROI = (売上貢献額 - 広告費 - 制作費) ÷ 制作費)。
リソース不足を解消し「質の高い資料」を継続的に作る体制
資料作成の「内製」と「外注」のメリット・デメリット
リソース制約の多い中堅・中小企業のBtoBマーケティング組織が、資料制作の課題を解決するためには、内製と外注の「メリット・デメリットを理解し、自社のフェーズに合わせて選択」する必要があります。
項目 | 内製(自社作成) | 外注(外部パートナー) |
|---|---|---|
メリット | 商材への高い専門性、低コスト(外注費削減)、ノウハウの社内蓄積 | プロの品質(デザイン・構成)、工数削減、第三者視点の獲得 |
デメリット | リソース圧迫、品質担保の難しさ(専門知識の属人化、デザイン)、工数超過リスク | 外注コスト、ノウハウの社内蓄積の難しさ、コミュニケーションコスト |
マーケティングを立ち上げたばかりのフェーズであれば、まずは外部パートナーを活用して「質の高い資料」を短期間で揃え、その構成やノウハウを学ぶことが、「内製化への近道」になります。
内製時の「工数削減」と「品質担保」のためのポイント
内製で資料作成を行う場合、「工数削減」と「品質担保」のトレードオフを解消するための工夫が必要です。
- 過去の一次情報を再利用する: 過去の営業資料や顧客からのヒアリング結果(導入事例、商談議事録など)から、顧客が本当に知りたい「生の声」や「課題の言語化」の要素を抽出し、コンテンツの核として再利用します。
- テンプレートを統一する: 資料のデザインを「テンプレート化」し、「デザイン工数を削減」します。これにより、デザインの「品質を担保」しつつ、コンテンツの内容作成に集中できる体制を作ります。
- 共同編集ツールを活用する: 複数人で資料作成を行う場合、Googleドキュメントなどの「共同編集ツール」で原稿を管理し、「部門間の連携ロスを削減」します。
貴社に最適な「外部パートナー」の選定基準
外部パートナーを選定する際は、単なる制作スキルだけでなく、「中長期的な事業成長への貢献」という視点を持つことが重要です。以下の評価軸を参考に、貴社に最適なパートナーを選びましょう。
- BtoB支援実績とノウハウの体系化: BtoB特有の「意思決定プロセスや購買行動」を理解しているか。「再現性のあるノウハウ」を保有し、それを自社で活用できる形で提供してくれるか。
- 戦略設計から実行支援までの一貫性: 資料作成の「手前(戦略設計)」から「その後(営業連携、ナーチャリング)」まで、一貫した支援が可能か。
- 柔軟な支援体制: 資料制作の代行だけでなく、「マーケティング人材の常駐」や「戦略設計コンサルティング」といった、企業のフェーズに合わせた柔軟な支援を拡張できるか。
2,000社以上のBtoBマーケティング支援実績から得た知見とノウハウを体系化し、戦略設計から施策実行まで柔軟に支援するferretソリューションは、中堅・中小企業のBtoBマーケティング担当者の課題解決を力強くサポートします。
【まとめ】BtoBサービス紹介資料は、稟議と営業を前に進めるためのツール
本記事では、BtoBサービス紹介資料が売上に貢献するための方法を解説しました。
- BtoB資料の役割は「社内検討と稟議を促進するツール」であり、BtoCの販促資料とは目的が異なります。
- 資料の成果は、構成やデザインではなく、「ターゲット・提供価値・競合優位性」を明確にした「戦略設計」が土台となります。
- 資料を「作って終わり」にせず、営業チームと連携し、「リードナーチャリング」の仕組みを構築することで、商談化率と受注率を向上させることができます。
- 資料の成果は、ダウンロード数ではなく、「商談化率」や「受注率」といった事業貢献度で評価すべきです。
サービス紹介資料は、担当者が「稟議を通すための武器」であり、営業が「受注を勝ち取るためのツール」です。この「社内稟議と営業活動を支援する」というBtoBならではの役割を理解し、その土台として「戦略設計」を徹底することが、成果を出すための最重要ポイントです。
BtoBマーケティングの戦略を見直したい方、リソース不足を解消したい方は、「2,000社以上の支援実績」と「体系化されたBtoBノウハウ」を持つferretソリューションのパートナー支援も選択肢としてご検討ください。
ferretソリューションのサービス資料ダウンロードはこちら
あわせて読みたい:成果につながるBtoBホワイトペーパーの作り方|CV率向上を実現する設計